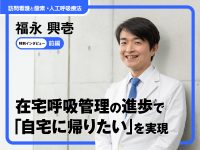ダニアレルギーはどんな症状が出る?見分け方と対処法・治療法

ダニアレルギーは、ダニの死骸やフンが原因で発症し、くしゃみや鼻水、皮膚のかゆみ、喘息などの症状を引き起こすアレルギー疾患です。ダニは目に見えないほど小さな生物ですが、私たちの生活空間に広く存在し、特に寝具やカーペットなどに潜んでいます。
本記事では、ダニアレルギーの症状や見分け方、発症時の対処法について解説します。訪問看護の利用者さんやご自身・ご家族の健康管理のためにも確認しておきましょう。
目次
ダニアレルギーとは
ダニアレルギーは、私たちの身の回りに存在するダニの死骸やフンが原因となって発症するアレルギー疾患です。アレルギーは、私たちの体の免疫システムが特定の物質(アレルゲン)を異物と認識し、排除しようとする反応のこと。ダニそのものが直接人体に害を及ぼすわけではなく、ダニの微細な粒子が空気中に漂い、吸い込むことでアレルギー反応を引き起こします。
最初にダニのフンや死骸が体内に入ると、免疫細胞が異物とみなして「IgE抗体」を作ります。これを「感作」といい、次にダニアレルゲンが体内に入った際、IgE抗体が反応します。そうすると、マスト細胞からヒスタミンなどの化学伝達物質が放出され、くしゃみ、鼻水、目や皮膚のかゆみ、気管支の炎症などのアレルギー症状が現れるのです。
ダニアレルギーの症状
ダニアレルギーの症状は、主に呼吸器症状と皮膚症状に分けられます。
呼吸器症状(くしゃみ・鼻水・咳・喘息など)
くしゃみや鼻水、鼻づまりといったアレルギー性鼻炎の症状のほか、咳が続いたり喘息を発症したりすることもあります。気管支が敏感な人は症状が重くなりやすく、夜間の咳や喘鳴(ゼーゼー・ヒューヒューする音)が生じることもあるため、早期の対処が必要です。
>>関連記事
アレルギー性鼻炎の種類&原因|訪問看護の場での対応方法・予防法
皮膚症状(湿疹・かゆみ・じんましんなど)
湿疹やかゆみ、じんましんなどが現れます。アトピー性皮膚炎の方は症状が悪化しやすい傾向にあります。かゆみが強く、かいてしまうことで皮膚が傷つき、二次感染を引き起こすことも。
ダニが繁殖しやすい季節と環境
ダニは高温多湿の環境を好み、気温20〜30℃、湿度60〜80%の条件で急激に増殖します。そのため、ダニの繁殖が最も活発になるのは梅雨から夏にかけてです。布団やカーペット、ソファ、ぬいぐるみなどの布製品にはダニが多く生息しており、こまめな掃除や換気をする必要があります。
また、冬場はダニの繁殖は落ち着くものの、暖房を使用することで室内が乾燥しやすくなり、すでに増えたダニの死骸やフンがハウスダストとして空気中に舞うことでアレルギー症状が悪化することがあります。
ダニアレルギーの対策
ダニアレルギーの症状を抑え、快適に生活するためには、環境管理が欠かせません。室内の清潔を保ち、アレルゲンの発生を抑えることで、症状の悪化を防ぐことができます。
室内環境の管理(掃除・換気・除湿など)
■湿度:
なるべく60%以下に保ちます。定期的に窓を開けて換気を行い、エアコン・除湿機等を活用して湿気をコントロールしましょう。
■掃除:
ダニのエサとなるホコリやフケを減らすために、こまめな掃除が大切です。掃除機を使う際は、フローリングや家具の表面だけでなく、カーペットや畳の隙間までしっかり吸い取りましょう。
ダニが繁殖しやすい布団やマットレスは防ダニカバーを使用し、シーツや枕カバーは週に1回以上洗濯するのが理想的です。布団乾燥機を活用すると、より高い効果が期待できます。カーペットはダニの温床になりやすいため、可能であれば撤去し、フローリングにしましょう。
なお、衣類も長期間クローゼットにしまっておくとダニが繁殖しやすいため、収納時は防ダニ収納袋を活用したほうがよいでしょう。また、衣替えをして時間をあけて着用する際は、洗濯することをおすすめします。
ダニアレルギーの症状が現れたときの対処法
ダニアレルギーの症状が現れた際の対処法についても見ていきましょう。
対症療法で症状を改善させる
ダニアレルギーによる発疹は、主に衣服で覆われる部分に現れ、赤みを帯びたしこりを生じるのが特徴です。かゆみが強く、無意識にかいてしまうことで皮膚が傷つき、さらに炎症が悪化することがあります。そのため、症状が出た際には、医師の指示に従ってステロイド外用薬を用いて早めに炎症を鎮めます。かゆみがひどい場合には、抗ヒスタミン薬を服用します。
免疫療法で根本から治せる可能性も
免疫療法は、アレルギーの原因となる物質(アレルゲン)を少しずつ体内に取り入れ、過剰な免疫反応を徐々に弱めていく治療法です。症状を一時的に抑える対症療法とは異なり、根本的な体質改善を目指します。
ダニアレルギーの免疫療法には、皮下免疫療法(SCIT)と舌下免疫療法(SLIT)の2種類があります。皮下免疫療法は、アレルゲンを一定の間隔で注射しながら体を慣れさせる方法で、主にアレルギー性鼻炎・アトピー型喘息が適応。一方、舌下免疫療法は、アレルゲンを含んだ薬を舌の下に置いて体内に吸収させる方法で、現状ではアレルギー性鼻炎のみが適応とされます。どちらも数年単位の継続が推奨されており、SLIT はアナフィラキシーをはじめとした全身副反応が比較的少ないといわれています。
なお、小児については、本剤を適切に舌下投与できると判断された場合にのみ使用可能ですが、5歳未満の幼児に対する安全性は確立されていません。どちらを選択するかは、年齢や症状の現れ方、検査結果など、さまざまな情報をもとに医師が判断します。
* * *
ダニアレルギーは、日々の環境管理を徹底することで症状を軽減できる疾患です。こまめな掃除や換気、寝具の適切な管理を心がけることで、アレルゲンの発生を抑え、快適な生活を送ることができます。今回、解説した内容をご自身やご家族の体調管理、利用者さんのアセスメントにお役立てください。
>>関連記事
梅雨の時期の感染症に注意!カビやダニによる感染症の症状や予防法を解説
| 編集・執筆:加藤 良大 監修:瀬尾 達(せお わたる)  医療法人瀬尾記念会瀬尾クリニック理事長。耳鼻咽喉科専門医。 クリニックでの診療の他、京都大学医学部講師や大阪歯科大学講師を兼任。 祖父から代々の耳鼻科医の家系。兄は、聖マリアンナ医科大学耳鼻科教授。 テレビやマスコミ出演多数。 |
【参考】
〇東京都福祉保健局.「健康・快適居住環境の指針― 健康を支える快適な住まいを目指して ―」
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/web_zenbun1
2025/5/9閲覧
〇日本アレルギー学会「ダニアレルギーにおけるアレルゲン免疫療法の手引き」(2018年6月29日)
https://www.jsaweb.jp/uploads/files/180618dani.pdf
2025/5/9閲覧